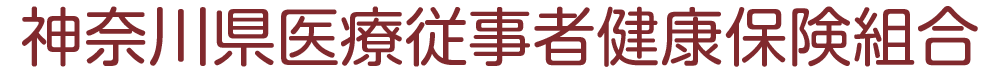健康保険の給付
事前に高額の医療費がかかると分かっているとき(限度額適用認定証など)
被保険者・被扶養者の方が入院・外来受診時に限度額適用認定証(非課税の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関等に提示すれば、窓口負担が軽減できます。
限度額適用認定証を医療機関等に提示できなかった場合は、「高額療養費支給申請書」を提出することで払い戻しが受けられます。
マイナ保険証の利用登録をすることで限度額適用認定証の申請が不要になりました
マイナンバーカードを被保険者証として利用登録したうえで、医療機関・薬局で、患者本人が情報提供に同意すると限度額適用認定証の区分が共有され、「限度額適用認定証」の提示をしなくても自己負担限度額までの支払いとなります。
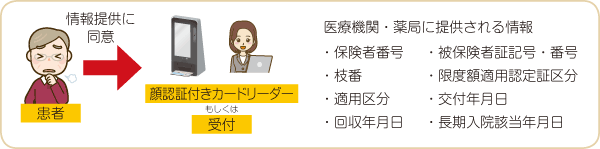
※低所得(被保険者が住民税非課税)の方は、専用の申請書に非課税証明書を添付のうえ、ご提出が必要です。
マイナンバーカードの被保険者証利用が未登録の場合
下記の流れで限度額適用認定証を申請し、受診時に窓口での提示が必要です。
- 申請書を記入して当組合へ送付
- 発行した認定証をご希望の住所へ送付します
- 被保険者証と共に医療機関等に提示
※70歳以上で発行対象の方は、認定証を事業所宛にお送りしますので、申請は不要です。
令和6年12月被保険者証廃止以降は変更の可能性があります。最新情報は随時お知らせいたします。
「限度額適用認定証」の区分
70歳未満の方(限度額適用認定証)
手続き
手続き書類
添付書類
- 負傷原因届
≪傷病の原因が外傷性(骨折・捻挫等)によるものであるときは添付してください。≫
手続き方法
- 当組合に上記申請書を提出(送付)してください。
後日「限度額適用認定証」をご希望の送付先へ郵送いたします。
発効年月日
当組合で申請書を受付した日の属する月の月初
例:令和6年4月20日に受付した場合、発効年月日は令和6年4月1日となります
有効期限
原則、発効年月日から8月31日まで
(9月以降発効の場合は翌年の8月31日までとなります)
限度額適用認定証提示後の自己負担限度額
| 認定証の 区分 |
所得区分 | 限度額適用認定証提示後の自己負担限度額 (【 】は4月目~) |
|---|---|---|
| ア | 標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)× 1% 【140,100円】 |
| イ | 標準報酬月額 53万~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)× 1% 【93,000円】 |
| ウ | 標準報酬月額 28万~50万円 |
80,100円+(医療費-267,000円)× 1% 【44,400円】 |
| エ | 標準報酬月額 26万円以下 |
57,600円【44,400円】 |
標準報酬月額とは、毎年、保険料を決めるため、収入を基に定期的に算出されているものです。
ご自分の標準報酬月額がわからない場合は、事業所の担当者にご確認ください。
70歳未満で市区町村民税が非課税世帯の方(限度額適用・標準負担額減額認定証)
手続き
手続き書類
添付書類
- 市区町村民税非課税証明書(被保険者本人が非課税であるかご確認ください)
- 負傷原因届
≪傷病の原因が外傷性(骨折・捻挫等)によるものであるときは添付してください。≫ - 長期入院(申請月以前の1年間で90日を超えて入院)された方は、入院期間を証明する書類(入院期間が記載されている領収書など)
手続き方法
- 当組合に上記申請書を提出(郵送)してください。
後日、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご希望の送付先へ郵送します。
発効年月日
当組合で申請書を受付した日の属する月の月初
例:令和6年11月20日に受付した場合、発効年月日は令和6年11月1日となります
有効期限
発効年月日から7月31日まで
(8月以降発効の場合は翌年の7月31日までとなります)
限度額適用・標準負担額減額認定証提示後の自己負担限度額
| 認定証 の区分 |
所得 区分 |
限度額適用・標準負担額減額認定証 提示後の 自己負担限度額 |
限度額適用・標準負担額減額認定証提示後の 入院時食事(生活)療養費の 標準負担額 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 低所得者 | 外来+入院 | 入院時食事療養費 (1食) |
入院時生活療養費 | |||
| 35,400円 | 多数該当 24,600円 |
210円 | 長期入院 160円 |
食費 (1食) 210円 |
居住費 (1日) 320円 |
||
70~74歳の方(高齢受給者証+限度額適用認定証)(一般の方)
「高齢受給者証」を提示することで自己負担限度額までの計算となります。ただし、下表の現役並みⅠ・Ⅱの区分の方は、医療機関等に「限度額適用認定証」の提示が必要となります。発行対象の方は、認定証を事業所にお送りしますので、申請手続きは不要です。
提示されない場合は83万円以上の方の限度額で計算されますのでご注意ください。この場合、高額療養費申請書の提出により、払い戻しが受けられます。
70歳から74歳の被保険者・被扶養者の方が医療機関等で受診される時の負担割合を表すもので、被保険者証と合わせて窓口で提示してください。
高齢受給者証は、原則として、加入時もしくは該当者の誕生月の中旬に事業所あてに送付いたします。
標準報酬月額ごとにより負担割合が「1割」「2割」「3割」に区分されます。
限度額適用認定証提示後の自己負担限度額
| 認定証の 区分 |
所得区分 | 限度額適用認定証提示後の自己負担限度額 (【 】は4月目~) |
|---|---|---|
| ― | 標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)× 1% 【140,100円】 |
| 現役並みⅡ | 標準報酬月額 53万~79万円 |
167,400円+(医療費-558,000円)× 1% 【93,000円】 |
| 現役並みⅠ | 標準報酬月額 28万~50万円 |
80,100円+(医療費-267,000円)× 1% 【44,400円】 |
| ― | 標準報酬月額 26万円以下 |
57,600円【44,400円】 |
70~74歳で市区町村民税が非課税世帯の方(限度額適用・標準負担額減額認定証)
手続き
手続き書類
添付書類
市区町村民税非課税に該当する方(低所得者ll ※下表参照)
- 市区町村民税非課税証明書
- 負傷原因届≪傷病の原因が外傷性(骨折・捻挫等)によるものであるときは添付してください。≫
市区町村民税非課税に該当する方で、被保険者及び被扶養者の所得が一定基準に満たない方(低所得者l ※下表参照)
- 市区町村民税非課税証明書(被保険者及び被扶養者に関するもの)
- 所得に関する証明書類
1.公的年金等源泉徴収票
2.給与等源泉徴収票 - 負傷原因届≪傷病の原因が外傷性(骨折・捻挫等)によるものであるときは添付してください。≫
手続き方法
- 当組合に上記申請書を提出(郵送)してください。
後日、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご希望の送付先へ郵送します。
発効年月日
当組合で申請書を受付した日の属する月の月初
例:令和6年11月20日に受付した場合、発効年月日は令和6年11月1日となります
有効期限
発効年月日から7月31日まで
(8月以降発効の場合は翌年の7月31日までとなります)
限度額適用・標準負担額減額認定証提示後の自己負担限度額等
| 区分 | 限度額適用・標準負担額減額認定証提示後の自己負担限度額 | 限度額適用・標準負担額減額認定証提示後の入院時食事(生活)療養費の標準負担額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外来 | 外来+入院 | 入院時食事療養費(1食) | 入院時生活療養費 | |||
| 低所得者ll | 8,000円 | 24,600円 | 210円 | 長期入院 160円 |
食費(1食) 210円 |
居住費(1日) 320円 |
| 低所得者l | 8,000円 | 15,000円 | 100円 | - | 食費(1食) 130円 |
居住費(1日) 320円 |
低所得者ll:同一世帯の全員が住民税非課税の世帯に属する人、または低所得者llの適用により生活保護とならない人
低所得者l:同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人、または低所得者lの適用により生活保護とならない人
よくあるご質問
限度額適用認定証は発行までにどれくらい日数がかかりますか?
原則、当組合にて申請書を受け付けた当日に、申請書記入のご住所に送付いたします。
限度額適用認定証はいつから使用ができますか?
発行された限度額適用認定証には、有効期間があり、その期間の範囲において使用ができます。この有効期間の始まり(発効年月日)は、当組合にて申請書の受付した日の属する月の初日となります。(さかのぼっての発効はできません)